立秋を迎えると、暦の上では秋。
しかし実際には蒸し暑い日が続き、体にはまだ夏の疲れが残っています。
この「残暑」の影響を放置すると、秋の不調(咳・だるさ・食欲低下など)につながることも。
今回は、秋を元気に迎えるための残暑ケアをご紹介します。
残暑が肺と脾に与える影響
東洋医学では、秋は「肺」と深く関わる季節。
乾燥や朝晩の涼しさで弱りやすくなりますが、残暑の時期は高温多湿で「脾」にも負担がかかります。
特に冷たい飲食や冷房の当たりすぎは、消化力を落とし、免疫力やエネルギー不足の原因に。
以前の記事(→ 残暑バテと脾のSOSサイン)では、脾を守るセルフケアをご紹介しましたが、この時期は肺の予防ケアも合わせて行うことがポイントです。
食養生で季節の変わり目をサポート
残暑から秋への移行期は、冷たいものを控え、温かい汁物や消化の良い食材を意識しましょう。
肺を潤す白い食材(梨・れんこん・大根)や、脾を補うかぼちゃ・さつまいももおすすめです。
酸味のある食材(梅干し・酢の物)は、秋の乾燥から体を守る働きもあります。
冷房での冷えや体のだるさが気になる方は、過去記事(→ エアコン冷えによる不調対策)も参考にしてください。
ツボ押しと生活リズムで整える
肺の養生には「尺沢(しゃくたく)」、脾の養生には「足三里(あしさんり)」が役立ちます。
お風呂上がりや就寝前に、心地よい強さでゆっくり押してみましょう。
仮眠はスマホやPCを早めに切り上げ、深い呼吸を意識することで、自律神経を整えやすくなります。
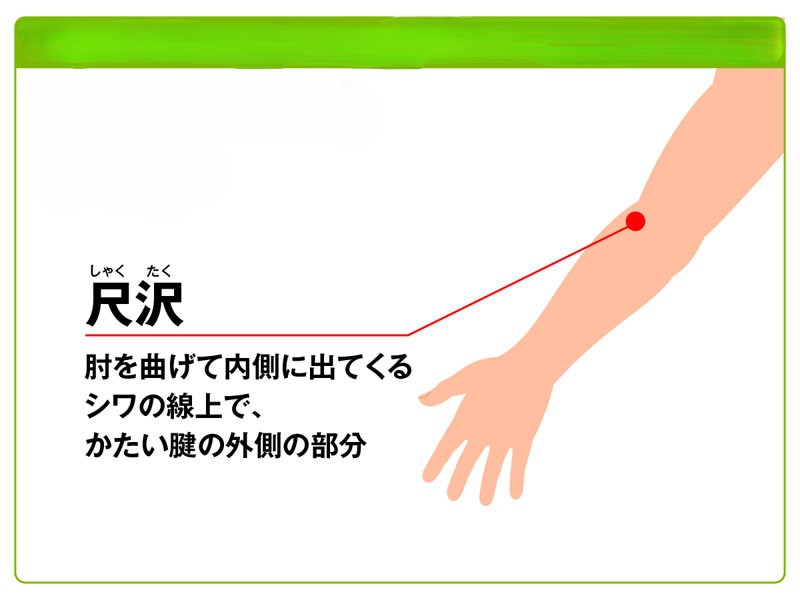
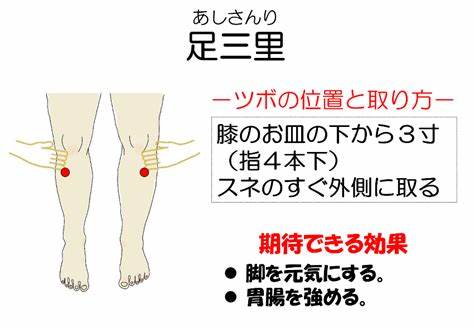
生活リズムが乱れやすい方は、過去記事(→ 肺を元気にする呼吸法)を取り入れてみると、朝から軽やかに動ける体づくりにつながります。
まとめ
立秋からの時期は、まだ残暑の影響が体に残っているため、肺と脾をバランスよくケアすることが大切です。
食養生・ツボ押し・生活習慣の見直しで、秋の不調を防ぎ、心地よい季節の変わり目を迎えましょう。








